

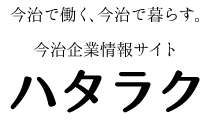
今治で活躍している人にインタビュー
玉川エリアで農業を営む森さん。お話を聞いているうちに、いつの間にかテーマは農業からまちづくりへと広がっていった。農業・地域・まちづくり、どれも森さんにとっては大事な仕事であり、切り離せないもの。ライフワークと呼べるのかもしれない。

今治市の山間部、自然豊かな玉川町に「森のともだち農園」ができたのは、森さんが高校生の時だったという。町営の直売所ができることになったのをきっかけに、まちづくりに熱心な母親と農業が得意な祖父が、新しい地域の特産品作りに取り組んだのがきっかけだった。
玉川町の気候風土に合ったブルーベリーとマコモタケの栽培をすると同時に、自分たちが生まれ育った里山を知ってもらいたいと、自然体験ができる農園の形を作ったという。「森のともだち農園」と、ちょっと変わった名前になったのは、みんなが集い発信できる場になるようにという想いが込められている。


当時高校生だった森さんにとっては、家族の新しい事業よりも受験の方が大事だった。正直に言えば、都会へ出てみたかった。市内に進学先のなかった今治の若者にとって、大学進学は夢を叶えるための一つのステップだ。そして森さんは東京の大学へ進みシステムエンジニアを目指すのだが、在学中に実家の父親が病に倒れた。就職先も決まりかけ、幸い父親も一命を取り留めたのだが、卒業後は実家へ戻り農園を継ごうと心に決めた。
今治へ戻ることに後悔はなかったという。それよりも、東京で生活をしていく未来像が見えなかった。「一度は今治を出てみたい」夢を叶えたその先は、生まれ育った玉川の方が、森さんにとってはリアルだったのだろう。

今治へ戻ってからは、地域で仕事をしていくことに慣れようと懸命だった。農業はまったくの未経験だ。実際に体を動かして覚えていくしかない。毎日畑へ行って祖父から手ほどきを受け、愛媛県立農業大学校の担い手コースにも通い座学と実地でみっちり学んだ。
森のともだち農園のブルーベリーは、完熟を待って収穫する。熟したデリケートな実をすべて手摘みし、選別機にかけた上で、改めて熟れ具合やサイズなどを人の目で確認しながら丁寧に仕分ける。鮮度の証である果実表面の白いブルーム(果粉)が取れないよう慎重に扱うことは祖母から教わった。

年に一度の収穫に向け、残りの期間は剪定をし、肥料を施し、消毒などの地道な作業を繰り返す。下草の刈り方も工夫を重ね、近年の気候の変化にも気を配る。今では50アールの土地に1,200本ものブルーベリーを管理するまでになった。
こうして農園を受け継いでいく一方で、頭にあったのは「この場所で自分は何をしていくべきか」ということ。自然体験施設を整えたり、ブランディング力を上げようと仕事を選んだりもしたが、なかなか思ったように形にならない。このままでいいのだろうか?模索する日々が続いた。

森のともだち農園には東京や大阪などの都市圏にも取引先がある。ビジネスとしてのメリットは大きいが、ひとたび有事が起これば小さな農家などは数字で関係を切られるシビアさもある。その一方で、どんな時も変わらずブルーベリーを求めてくれたのは地元だった。それを身を持って知ったのが、2020年のコロナ禍だ。地域のつながりが、しんどい時を支えてくれた。
またコロナ禍は、地域の祭りや高齢者の寄り合い、婦人会、子育てサロン、そして地元スーパーの撤退など、人と人とのつながりを次々と奪っていった。危機感を覚えた森さんは「地域のために小さな拠点を作りたい」と決意する。自治体が募集するガバメントクラウドファンディングに応募し、プロジェクトを立ち上げた。キッチンカーは小さな拠点になる。自由に移動もできて、地域の寄り合いに気軽に出店したり、万一の災害時も温かい食事を出すことができる。そう支援を呼びかけ、見事目標金額を達成させた。

「以前は都市圏から愛媛へ経済を回そう、そんな感覚で商売をしていたんですが、本当に目指すべきところは、いかに地元の人たちに認められるか。それを感じたのがコロナ禍でした」と振り返る。地域のコミュニティ再建を目指したキッチンカーは今、幼稚園から高齢者サロン、各地のマルシェでも活躍中だ。
相談された仕事は基本的に断らない、森さんはそう心に決めている。見せてくれた夏のスケジュールは、毎日びっしり予定が書き込まれていた。一年で一番忙しいブルーベリーの収穫に加え、自然体験の受け入れから、婚活イベント、小学校でのホラーナイト、そして地元中学校の教育講座まで多種多様だ。
「玉川エリアで自分ができることをやっていく。これが僕のキャラクターかな」ここ1〜2年で自分の立ち位置がわかってきたと語る森さん。相手は自分ならできると思って声をかけてくれている。それに向けて取り組めばなんとかなるんですよ、と頼もしい。ある時はサイクリングイベントで500人分ものフィニッシュフードをキッチンカーで提供した。その結果が自分たちのスキルとして残る。その積み重ねなのだ。


今年は初めて「ふるさとワーキングホリデー」の若者を受け入れた。一定期間農園に滞在し、働いて収入を得ながら休日も楽しんでもらうものだ。ある学生から「こんな働き方もあるんですね」と言われたという。遊んでいるように見えたなら伝わったかな、と森さんは笑う。人は形式の中で生きていくだけではない、様々な選択肢がある。都会での就職が決まっている彼らにそれが伝わればいい。
森さんの仕事には、様々な思いがあふれていた。地域を、まちを、自然を守りたい。それが産業を守り、未来の子どもたちへの財産になる。だから農業も地域のことも、目の前のことに全力で取り組む。「むちゃくちゃやった方が楽しい」そんな姿勢が清々しく見えた。
