

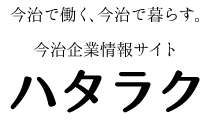
今治の隠れた名所を、いまばりバリィさんが訪ねます
中心を今治の大動脈、国道196号バイパスが貫く乃万地区。松山方面へ向かう幹線道路とあって、周辺には商業施設が並び、車もひっきりなしに行き交います。この乃万地区にたくさんの宝物があると聞いてバリィさんがやってきました。

バリィさんがまず訪ねたのは、「のまうまハイランド」です。乃万地域の中央あたりに位置し、小高い山の斜面に3つの放牧場や乗馬コースが広がります。子ども向けの遊具や小動物とふれあえるスペースなどもあり、家族連れが休日を過ごしたり、小学生が遠足に訪れることもあるという今治市民におなじみの憩いの場になっています。
ここで飼育されているのが日本固有の馬、在来馬の一種である野間馬です。体高は約120cmとバリィさんよりも小さな馬で、在来馬のなかでも最小なのだそう。ずんぐりとした体に太い足、長いたてがみが特徴です。小さな身体で力持ち!なのですが、優しい目とおだやかな性格で子どもたちの人気者だといいます。そんなかわいらしい野間馬ですが、一時は絶滅の危機にありました。

そもそも野間馬の歴史は古く、江戸時代にさかのぼります。お殿様の命で合戦に使う馬を乃万(当時の野間郡)の農家が育てることになったことから始まります。大きい馬には報奨金が与えられ、小さい馬は無償で農家に払い下げられたことで野間馬がこの地に生まれました。
野間馬は収穫したみかんを運ぶ馬として活躍します。重いみかん箱を載せて力強く歩き、丈夫で賢く農耕馬としてもよく働く野間馬は、当時の農家にとって大切なパートナーでした。ところが明治になると軍馬養成のため小さな馬を育てることが禁止されてしまいます。さらに時代の流れで農業が次第に機械化されていくと野間馬の数は急激に減り、昭和30年代にはついに今治に野間馬がいなくなってしまいます。


そこに現れた救世主が、松山市で野間馬を守り育てていた長岡悟氏でした。1978(昭和53)年、氏によって貴重な4頭が今治市へ寄贈され、野間馬の命がふるさとに受け継がれたのを機に野間馬保存会が発足。のまうまハイランドには現在54頭(令和7年1月現在)の野間馬たちが、保存会の方たちの手により愛情を込めて守り育てられています。

のまうまハイランドを後にしたバリィさん、道端で見つけたのは、何やらおごそかな雰囲気の看板です。なになに、「重要文化財」と書かれているではありませんか。これは正しく宝物!そう、野間地区は鎌倉時代から南北朝時代にかけて造られたという石造物が点在することで知られています。田んぼの中や民家の間など、「こんなところに!」という場所に石塔が佇む風景が見られます。

通称「覚庵(かくあん)」と呼ばれるのは、田んぼのなかに並ぶ大小2基の五輪塔。鎌倉時代後期のものと言われますが、長い歴史を感じさせないほど美しい姿のまま残っているのが印象的です。五輪塔とは、丸や四角、三角など5つ石が積み重なった石塔をいい、上から空・風・火・水・地を意味するインドの五大思想を基に日本で独自に発展。お墓や供養塔として建てられました。こちらの覚庵も、この地の領主であった岡部十郎夫妻の墓と伝わります。何百年もの間、寄り添い地域を見守ってきた石塔に夫婦の姿が重なるようです。

覚庵から歩いて10分ほどの距離にあるのが、長円寺跡に残る宝篋印塔(ほうきょういんとう)です。背面に刻まれた銘文によれば1325(正中2)年の作で、こちらも鎌倉時代の秀作。宝篋印塔も、供養塔や墓碑塔として建てられてきたもので、「宝篋印陀羅尼(ほうきょういんだらに)」という経典を納めて供養することで現世での罪を消し功徳を得られると大切にされてきました。
こちらの宝篋印塔は高さおよそ3.6mと全国屈指の大きさといいますから、当時の人々の厚い信仰心が想像されます。また基礎と塔身の間にみられる受け座にも注目。「越智式」と呼ばれるこの地域特有のデザインなのだそう。他の宝篋印塔も見てみたくなりますね。


すぐ近くには「馬場五輪塔」もあり、ぶらりと歩いて回れる範囲に重要文化財の石塔を3基も見ることができるのですが、これってすごいことなのでは?実は愛媛県には国の重要文化財に指定された石造物が23基あり、京都・奈良・滋賀に続いて全国4位の数。それだけでも驚きですが、なんとそのうちの16基が乃万に集中しているというのですから、なおびっくりです。これらの石塔は、周辺地域に記された「石造物と野間馬の小路」という看板を頼りにたどることができます。
にぎやかな国道を一歩入ってみれば、知らなかった乃万地区の顔が見えてきました。のどかな田園風景のなかに野間馬たちがのんびり草をはみ、何百年もの時を経て乃万の人々の暮らしを見守ってきた石造物。車の速度では見逃してしまう、大切な宝物がそこにありました。次の週末は、乃万を歩いて散策してみませんか?バリィさんは野間馬さんとすっかり仲良くなっちゃったみたい。

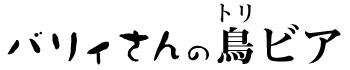
乃万に残る16基の石造物のうち11基が集まるのが、延喜にある乗禅寺です。五輪塔が4基、宝篋印塔が5基、宝塔が2基、周辺に散在していた石塔群をまとめ、1704(元禄17)年に本堂の裏手の山に保存されました。もちろんすべてが国の重要文化財に指定されています。いずれも鎌倉時代から室町時代初めの作で、五輪塔の最大のものは後醍醐天皇の供養塔と伝わります。乃万の人々の信仰の深さ、文化の高さ、そして当時の職人の技がうかがえる大切な文化財です。


「継ぎ獅子」は、毎年5月に今治市内各地で行われる春祭りの恒例行事。大人の肩にもう一人大人が立ち、さらに「獅子児」と呼ばれる子どもが上がり、「トン・トトン」という太鼓のリズムに合わせて扇や鈴を持って舞う姿は圧巻。天においでる神様に近づきたいと、三継ぎ、四継ぎとだんだんと高くなっていったと伝わります。
特に野間神社の春祭りは先陣を切って行われ、石段の上で演じられる継ぎ獅子がスリル満点!ポーズを決めた瞬間、集まった氏子のみならず観光客からも盛大な拍手喝采が送られます。

